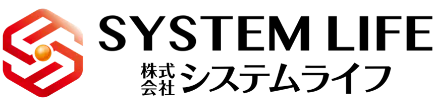車輌輸送を行う事業者にとって、自社の業務にフィットするパッケージシステムを見つけるのは簡単ではありません。結果としてExcelでの管理に頼らざるを得ず、業務の煩雑化や属人化に悩まされている現場も多いのではないでしょうか。本記事では、DXによる業務改革を進めるために押さえておきたい、システム選定やベンダー選びのポイントを解説します。「車輌輸送に必要な機能とは?」「他社はどう管理しているのか?」といった疑問に答えながら、システム導入のヒントをお届けします。
目次
なぜ車輌輸送システムのパッケージ化は難しい?
車輌輸送はそもそも取り扱う企業数が少なく、非常にニッチで複雑な業務領域です。汎用的な運送管理システムでは対応が難しく、車輌輸送に特化したパッケージシステムはほとんど存在しないのが現状です。その結果、いまだにExcelなどによるアナログ管理が主流となっており、業務の属人化や非効率が課題となっています。しかし裏を返せば、こうした業務こそシステム化による効果が大きく、改善の余地が大きいとも言えます。実際にシステム導入を検討する際には、既存のパッケージシステムをベースにある程度のカスタマイズを行うか、あるいはスクラッチで一から開発するか、いずれかの選択が必要になります。
どちらのケースでも共通して重要なのは、車輌輸送業務の特性を深く理解しているベンダーの存在です。車輌輸送は、一般的な運送とは異なる独自の業務フローや管理項目が多いため、業務に即した柔軟なシステム設計が求められます。単なるシステム提供ではなく、業務理解に基づいた提案・構築ができるパートナー選びが、成功の鍵を握ります。
車輌輸送を行う運送会社の業務特性とは
車輌輸送業務は、単に「車を運ぶ」だけではありません。扱う車輌の種類や状態、輸送方法、配車の組み方、運賃の算出方法など、あらゆる工程において一般的な運送とは異なる独自の管理が求められます。ここからは、車輌輸送を行う運送会社が直面する具体的な業務特性について、代表的なポイントをいくつかの観点から詳しく見ていきましょう。
運ぶ荷物は「クルマ」≫品名管理の特殊性
一般的な運送管理システムでは、品名入力欄は1つのケースが多いです。しかし車輌輸送では、メーカー・車種・型式・登録番号・車台番号・色など、1台の車に対して複数の情報を管理する必要があります。特に集荷時には、メーカーや色といった情報をもとに荷積みを行うため、運行指示書にはこれらの項目が明確に記載されている必要があります。そのため、パッケージシステムを利用する場合には、これらの情報を1つの品名欄に羅列して登録するなどの運用が行われることもあり、現場の利用者にとっては分かりづらく、ミスの原因になることもあります。
積載台数・位置が変わる ≫キャリアカー配車の難しさ
キャリアカーによる輸送では、1台積みから最大8台積みまで対応可能ですが、1台積みを除けば多くが混載輸送となります。配車時には「何台積みで運ぶか」を前提に計画を立てますが、商品車の車種によって積載可能な台数や位置が異なるため、単純な割り当てでは対応できません。特に混載輸送では中継地点を挟むケースも多く、積載位置は中継順を考慮して決める必要があります。こうした複雑な条件を踏まえて配車を行うため、業務は属人化しやすく、システム化による支援が強く求められる領域です。
中継×積み替えが当たり前 ≫車輌輸送ならではの複雑さ
先にも触れたように、車輌輸送では単純にA地点からB地点へ運ぶだけでなく、中継が発生するケースが非常に多くあります。一般的な輸送でも中継はありますが、車輌輸送の場合は中継地で車両を一度降ろした後に、ナンバーカットなどのメンテナンス作業を行ったり、別のキャリアカーに積み替えて再出発したりするなど、より複雑な運用が求められます。混載輸送や中継輸送のいずれかに対応したパッケージシステムは存在しますが、車輌輸送では両方に同時対応できることが求められるため、システム選定の際には注意が必要です。
事前に決まらない輸送内容 ≫柔軟な配車が求められる現場
新車輸送の場合、ディーラーからの注文状況や工場での生産スケジュールが日々変動するため、工場に到着するまで最終的な配送先が確定しないこともあります。また、オークション会場間の輸送では、当日現地に行ってみないと(落札結果が出るまで)輸送対象となる車両の台数が分からないことがほとんどです。このように、事前に「この車種の商品車を運んでほしい」といった明確な指示が出せないケースが多く、従来の配車の仕組みでは対応しきれない場面が少なくありません。
単純なタリフ表では対応できない ≫車輌輸送の運賃設定
車輌輸送では、同じ車種であっても運賃が一律ではありません。距離や重量といった基本的な要素だけでなく、新車か中古車かといった区分や、車両の状態・輸送方法など、運賃を決定づける要素が複数存在します。そのため、単純なタリフ表(距離×重量)では対応しきれず、これらの条件を細かく管理できる仕組みが必要です。特に、区分ごとの運賃設定や条件分岐が可能なシステムでなければ、正確な運賃管理が難しくなります。
車輌輸送の中核、配車機能のポイント
車輌輸送業務の中でも、特にシステム化が難しいのが「配車業務」です。積載台数や車種の組み合わせ、中継地点の有無など、考慮すべき要素が多く、属人化しやすい領域でもあります。ここでは、車輌輸送における配車機能のポイントを3つの観点から整理します。
キャリアカー配車の最適化機能
配車担当者は、輸送先(ヤード・ディーラー・個人宅)に応じてキャリアカーの種類を選定し、積載台数や回転率を考慮して配車計画を立てます。車種ごとのサイズやステータス(自走可否・改造の有無など)に応じた積載位置の調整や、積み合わせパターンの記憶による標準化機能があると、業務効率が大きく向上します。
混載×中継に対応する柔軟な配車設計
荷主や発着地が異なる車両を、方面が同じだからと途中まで混載で運び、中継地点で積み替えるケースも多くあります。また、路上での積み下ろしができないため、ディーラーの都合に合わせて小型キャリアカーに乗せ換えるなどの対応も必要です。こうした複雑な配車には、方面別配車や中継地の管理、営業所の切り替えに対応できる機能が求められます。
複合一貫輸送に対応するシステム機能
車輌輸送では、陸送だけでなく船舶を使った輸送も発生します。自走でフェリーに乗せるのか、キャリアカーごと乗せるのか、トラクタヘッドを連結したままかなど、輸送方法によって管理項目が変わります。また、一時保管を行う場合はロケーション管理も必要となるため、メーカーごとの物流パターンに対応した柔軟なシステム設計が重要です。
車輌輸送システムの構築事例
Excelによる配車管理に限界を感じていたある車輌輸送会社では、属人化や二重入力、配車ミスといった課題を抱えていました。そこで、車輌輸送業務に特化したシステムを導入し、配車・日報・売上管理を一気通貫で連携できるように構築。配車ボードのビジュアル化により、誰でも配車業務を行えるようになり、属人化の解消に成功しました。また、受注データをもとに日報や請求処理まで自動連携できるようになったことで、業務の手間が大幅に削減。結果として、業務効率の向上と利益の可視化を同時に実現しています。
まとめ
車輌輸送業務は、一般的な運送とは異なる複雑な業務特性を多く抱えており、従来の汎用的なシステムでは対応しきれない場面が少なくありません。配車や積載、運賃計算、中継管理など、現場で求められる機能は多岐にわたります。だからこそ、業務に即した柔軟なシステム構築が不可欠であり、業務理解のあるベンダーとの連携が成功の鍵を握ります。実際の導入事例でも、一気通貫のシステム化によって属人化の解消や業務効率化が実現されており、車輌輸送業務のDXは確実に成果を生み出しています。本記事が、次期システム選定や業務改善の一助となれば幸いです。