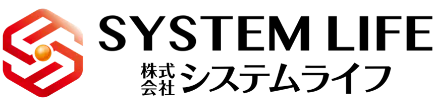「送り状発行システムを導入したい」通販需要拡大による宅配事業への新規参入や、路線便を使った輸送コスト低減などを背景に、送り状発行の効率化・システム化を検討される事業者様が増えてきました。送り状発行では、荷物追跡No.の発番や仕分けのための着店表示など、いくつかの注意点があります。この記事では、送り状発行の基本からシステム構築のポイントまで解説します。
目次
送り状発行の基本
送り状発行が必要な場面とは
路線便配送では、複数の配送拠点を経由し、リレー方式で効率的に荷物を配送します。配送拠点では、各地で荷受けされた荷物が集まり、それを仕分けたうえで、同じ方面の荷物をまとめてトラックに載せることになります。路線便配送では輸送効率を高めるのと引き換えに混載輸送が前提であり、お届け先はバラバラ、どれをどこまで運べばよいのか荷物に表示する必要があるわけです。そこで送り状(配送伝票や宅配伝票)を必要とします。
送り状の役割とは
路線便配送のプロセスから送り状の役割を考えると、大きくは次の3つです。①はお届け先の氏名・住所情報のことで、②は「着店」、③は送り状No.を指します(詳しくは後述)。
≪送り状の役割≫
混載なので、荷物のお届けが先がバラバラ →役割①お届け先の表示
配送拠点で方面別仕分けが必要 →役割②仕分けの目印
配送プロセスが複雑で、届くまでに時間を要する →役割③荷物のトレーサビリティ
送り状に印字しなければならない情報とは
送り状の印字項目は配送形態等によって若干変わりますが、それでも上記①②③を満たすことは送り状の共通要件です。よくある印字項目としては、おおよそ以下のようなものかと思います。
≪送り状に表示する情報(例)≫
送り状番号 :※荷物トレーサビリティ用
出荷情報 :出荷日、注文番号、配達指定日など
お届け先情報:住所、氏名など ※ここの郵便番号から着店を決める
集荷先情報 :住所、氏名など ※ここの郵便番号から発店を決める
依頼主情報 :住所、氏名など ※送り状の依頼主欄に、集荷先以外の名前を指定する際に必要
送り状情報 :個口数、代引き情報(金額や決済手段含む)など
梱包情報 :サイズ区分(80サイズや100サイズ)など ※この情報と発着店で運賃を決める
送り状発行システム構築のポイント
送り状発行システムの注意点を5つのポイントに分けて解説します。
ポイント①送り状No.
送り状No.は、「11桁または12桁の数字で構成する」とルールで決められています。0000-0000-0001から1つずつカウントアップした連番を振ることもできますが、そうするとある問題が生じます。例えば、荷物の到着を待っている人が300番を問い合わせようとして誤って30番とシステムに入力した場合、知らない誰かの30番の荷物情報が表示されてしまうのです(連番なので30番の荷物も存在する)。このような入力ミスを未然に検知できる仕組みがチェックディジット(CD)で、通常は連番+下1桁をCDナンバーとして送り状No.を生成します。
ポイント②発着店
荷受けを行った時点で【発店】は決まりますが、配送拠点がいくつもある場合、そのうちのどこを【着店】に設定すればよいのでしょうか。人が個別に判断するのはあまりに大変なため、通常は、お届け先住所の郵便番号をもとに送り状発行システムで自動判定を行います。事前に【着店】の管轄エリアを設定しておくことで(総務省HPで公開されているJIS規格の市区町村コードデータを使うことが多い)、この処理が可能になります。集荷先でハンディ端末を使って、着店ラベルをその場で出力するやり方もあります。
ポイント③元払・着払
配送料金の徴収状態(元払or着払)を明示するのも、送り状の役割です。配送料金の計算については、送り状発行システムが「WMSから出荷データを受け取って、送り状を発行するだけのシステム」であれば特に考慮する必要はありませんが、注文受付~売上登録を送り状システム側で担う場合は、料金計算機能まで実装する必要があります。着払いの場合はお届け先で金銭の授受を行うことになるため、送り状と一緒に請求書・領収書フォームをくっつけて印刷する方法がよくとられます。
ポイント④代引き
特に通販商品の配送を行っている場合に注意しなければいけないのが、「代引き」の荷物です。着払い同様、代引き荷物もお届け先で金銭の授受を行うので、領収書・請求書が必要になります。配送料の支払いである着払いとは異なり、商品代金はお店が決めたもの(=出荷データに含まれている情報)なので、送り状発行時点で商品代金を印刷しておくのが普通です。商品代金の金額によっては、領収書に収入印紙欄を印字することもあります。
ポイント⑤プリンタ
送り状を何に印刷するかで、準備しなければならないプリンタも変わります。複写式伝票の場合は高額なドットプリンタが必要ですが、最近はシールタイプを使うことが多い印象です。またシールタイプにも2パターンあり、普通の複合機から出力するパターン(A5サイズのシール台紙を使用することが多い)と、ラベルプリンタからするタイプがあります。複合機とラベルプリンタでは印刷スピードが異なり、通常はラベルプリンタから出力するほうが、送り状1枚あたりの印刷速度が速くなります。
送り状はどのタイミングで発行する?
物流倉庫が送り状発行を行う場合
物流倉庫では、送り状による配送指示のほか、ピッキングリスト等による出荷作業指示が必ず発生します、そう考えると、ピッキングリストと送り状を同じシステム(WMSや検品システム)から同時出力するのが一番合理的です。データ連携作業が不要なので帳票が揃うまでにタイムラグがなく、システム構成がシンプル(=コスト最小限)になります。
しかしここで注意が必要なのが、送り状フォーマット。自社配送なら自由に設計できますが、配送業者が別に存在する場合、配送業者が指定するレイアウトやルール(送り状1件に対し複数個口OK/NGなど)に則って送り状を作成しなければなりません。配送業者ごとにフォーマットを準備するのは手間もコストもかかるため、送り状発行システムを配送業者側で準備したうえで配送を請け負うケースも増えています。その場合は、WMS~送り状発行システム間でデータインターフェースを構築します。
運送会社が送り状発行を行う場合
大手宅配業者の例では、集荷・荷受け時に作成することが多いかと思います。従来は専用の複写伝票に送り主が手書きして作成するのが主流でしたが、近年では集荷依頼をWebで受け付け、集荷依頼情報をもとに運送会社側が送り状を発行するケースも増えてきた印象です。当然サイズ情報などは集荷時にしか分からないので、そのような情報はハンディ端末を使って集荷時に情報追加します。
まとめ
路線便配送においては、送り状が荷物仕分けやトレーサビリティに大きな役割を果たします。そのために必要となる「送り状No.」や「発着店」をどのように決めるのか、まず考えなければなりません。またWMSや荷主システムなどと連携し、荷物の配送料金や商品代金の徴収有無を把握しておく必要もあります(場合によっては、送り状と一緒に請求書や領収書を出力する)。送り状を打ち出す紙・プリンタは、荷量や自社の事業形態を鑑みて選ぶことが大切です。
送り状発行システムとひとことに言っても、システムの在り方は事業者ごとに異なります。本記事を、システム検討のご参考として頂ければ幸いです。システムライフでは、送り状発行システムや配送管理システムについて、ご相談から承っております。