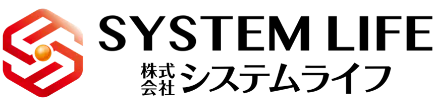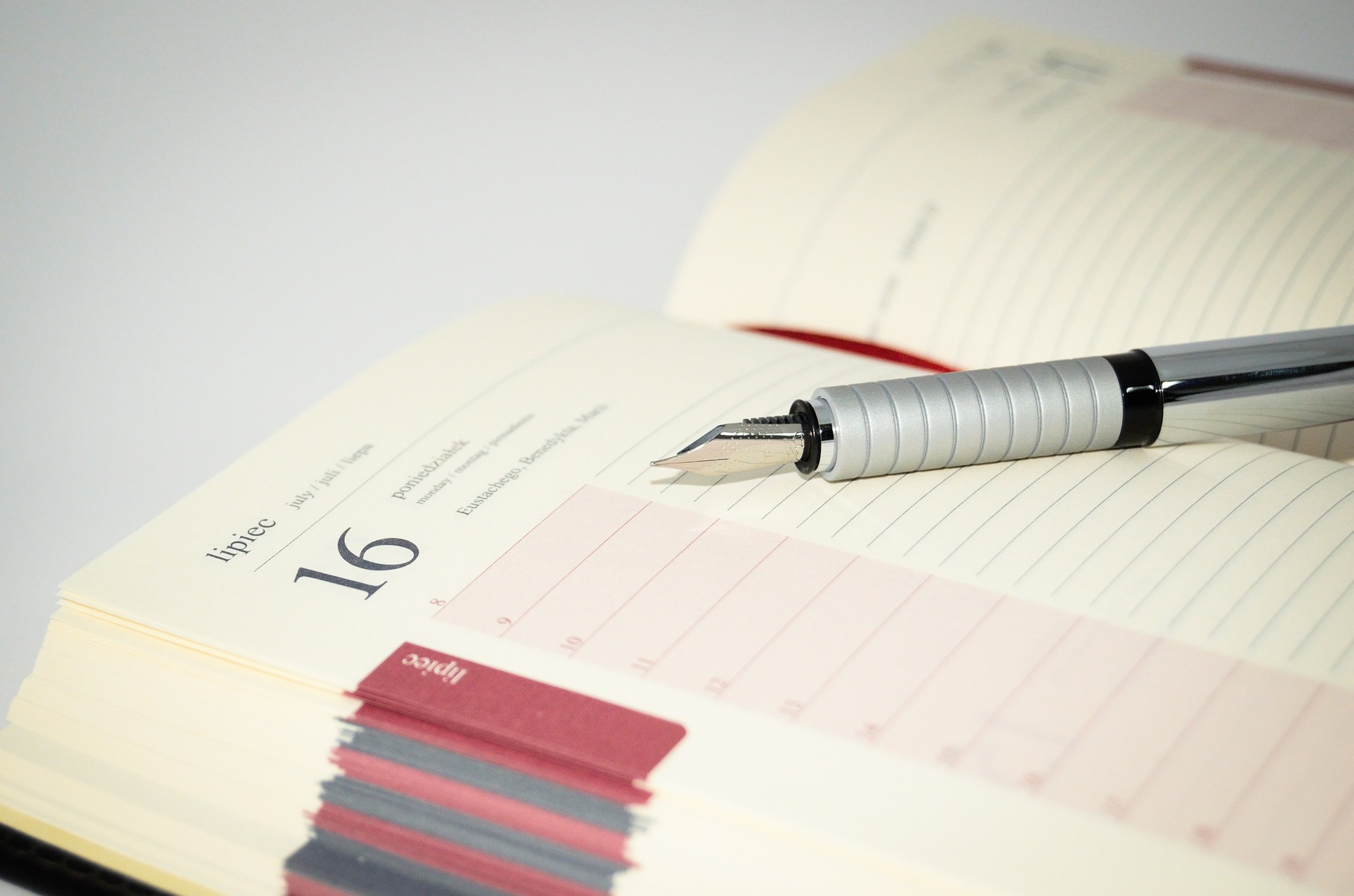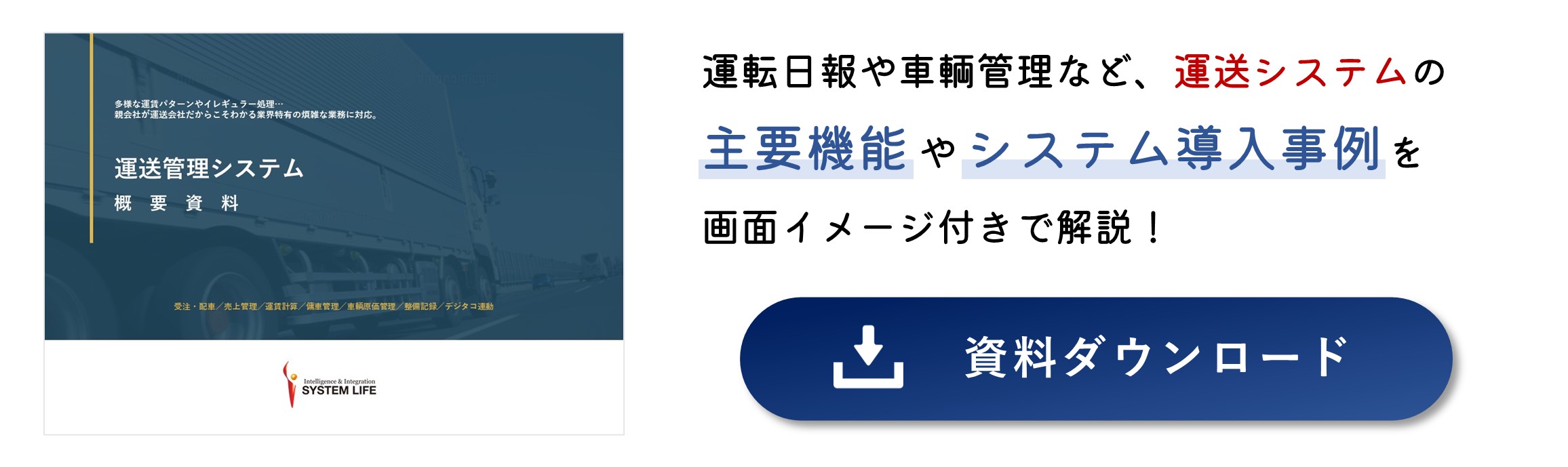「自社業務のどこを優先して改善すべきかわからない」。DXに取り組む運送会社様は増えていますが、DXした場合の具体的な機能・運用イメージが湧かない担当者様も多いかと思います。具体的な解決手段と自社にとって現実的な選択肢であるかのイメージができれば、取り組み(投資)の優先順位も決めやすくなります。本記事では、運送業の業務改善ポイントを3つの切り口にわけ、具体的なDX方法を解説します。
目次
業務改善のターゲットを定める
運送業でよく耳にする事業課題といえば、残業削減、人員不足解消、属人化解消、利益改善、安全性向上 などが挙げられます。これらの課題解決には、業務効率化しかありません。企業の悩みはたいてい複数の問題が絡み合って存在し、これが「どこから手をつけるべきか」という迷いに繋がります。
今回は業務改善のターゲットを考えるための切り口として「ドライバー業務」「配車業務」「事務・管理者業務」に切り分け、それぞれに効率化ポイントを解説していきます。運用変更、人員配置の見直し、コスト面などの観点から、取り組みの優先順位(ターゲット)を検討するのにご活用頂ければ幸いです。
ドライバー業務の効率化方法
ドライバー業務内容を(ざっくり)分解すると下記のとおり。ここから改善ポイントを探します。
・勤怠打刻(出退勤時間、残業など)
・運行前後の車輌点検
・乗務前/乗務後点呼
・輸送(運行)業務
・運転日報作成
輸送の安全性確保は、効率化より高品質化
輸送の安全は社会への影響が大きく、運送業が何より優先しなくてはならない課題です。それを考えると運行前後の車輌点検や点呼は丁寧に行われるべきで、(ムダを省く意味での)効率化優位の考え方は危険と言えます。ここで目指すべきは業務の高品質化で、DXによる改善を進めるとすれば、確認/認識漏れを無くすようなシステム構築が良いでしょう。
たとえば、点呼ソフト(アルコールチェッカー連携や点呼簿デジタル化)や、ドライバー見守りツール(健康状態を画像や脈拍データなどで可視化・分析)などがそれにあたります。
効率化ポイントは日報作成や勤怠管理
そうなるとドライバー業務の効率化ポイントは、運転日報作成や勤怠記録といった事務作業のムダをいかに省くか、の話になってきます。デジタコデータから日報や勤務実績を自動作成するのはもちろん、ドライバーがスマホを使って日報・勤怠入力をする事業者さまも増えているようです。デジタコだけでは本当の出退勤時間がわからなかったり、スマホは入力忘れのリスクが大きかったりと一長一短あるため、自社の管理体系にあわせて手段を検討する必要があります。
輸送業務そのものの効率化策とは
輸送業務のムリ・ムダ・ムラを省こうとすると、荷待ち時間の解消、荷役作業の見直し、渋滞回避などに取り組まなければなりません。運送会社単独での改善は限界があるなか、できることも少なからずあります。たとえば、空き車輌の位置を可視化して配車計画に融通をきかせたり(車輌動態管理ソフトや配車システムを利用)、荷主と交渉するための荷待ち/作業時間集計分析(運行管理システムを利用)などです。
配車業務の効率化方法
配車業務内容を(ざっくり)分解すると下記のとおり。ここから改善ポイントを探します。
・受注業務(メモや入力、仕分け)
・配車計画作成(車輌の空き確認、改善基準告示への対応、配車ボード共有など)
・運行指示書作成、連絡
・傭車手配(傭車先選び、空車確認、配車依頼書作成など)
受注情報のデータ化は全体改善に繋がる
受注は注文内容の記録や仕分けの手間が発生するので、受注そのものを電子化=Web受注するのが一番の理想です(※Web受注への移行は取引先に依存するためハードルは高い)。ただWeb受注までいかずとも、受注情報をシステム入力してデータ化さえできれば、受注仕分け自動化や、過去の注文データを活用した入力簡素化、後続の配車業務DX化が図れます。取り組む価値は大きいと言えるでしょう。
ちなみに、OCR(自動文字認識)でFAX注文を電子化する方法もありますが、手書きも様式も多い運送業ではまだまだ現実的な手段とは言えない状況です。
配車計画作成は、自動化or支援システムの2つの道
配車計画作成は自動化(自動配車)がトレンドではありますが、受注(積荷)と車輌を自動マッチングするための事前準備にそこそこの労力を要します。機械がベテランの配車マンと同じように判断して最適な配車を組むには、指定時間帯の車輌位置や積荷のサイズ、ドライバーの勤務状況、中継地設定に至るまで、数値化されたデータベースが必要なのです。
自動化ではないもう一つの選択肢として「配車支援システム」があり、ガントチャートによる配車/空車状況の見える化などで、効率化や脱属人化を図ります。配車支援システムの場合、機械が自動判定するための膨大なデータ登録は求められないため、自社に合った方法を選ぶと良いです。
尚、自動配車であれ配車支援であれ、配車DXには受注がデータ化されていることが必須条件となります。
傭車手配もオンライン化できるか
自社ドライバーへの配送指示や傭車先への配車依頼は、上記の要領で配車がシステム化できれば自動作成が可能です。受注と同じように傭車とのやり取り(発注)もオンライン上で完結できれば、依頼書をFAXしたり、その後の車番確認や運行後の実績確認まで効率化が図れるでしょう。ただ、これも受注と同じくオンライン移行できるかどうかは傭車先に依存するため、傭車先が喜んで使いたがる工夫が必要になります。
事務・管理者業務の効率化方法
事務・管理者業務内容を(ざっくり)分解すると下記のとおり。ここから改善ポイントを探します。
・請求、下払い処理
・ドライバーの勤怠/労務/給与管理
・車輌台帳管理(車検や整備記録など)
・車輌原価/損益管理、運賃管理(見直し検討など)
配車システムは、請求・下払い管理の合理化に繋がる
一般的な販売管理システムを利用する運送会社では、配車業務はExcelなどで管理し、運行が終わったら販売管理システムに売上/仕入(傭車)入力を実施することになります。上述した配車システムを導入するとシステム運用が受注スタートになるため、受注・配車データをもとに請求・下払い管理まで一気通貫で行えます。配車システムは配車業務の効率化だけでなく、データの二重入力も防げるというわけです。
ドライバーの勤怠・労務管理は業界特化型が吉
ドライバーの勤怠・労務管理は、出退勤や残業管理のほかに改善基準告示対応(拘束時間や休息時間、長時間運行の回数などの管理)が必要になるため、一般的な勤怠ソフトだけでは管理しきれません。ここでは業界向け専用パッケージの利用が、効率化への道です。ドライバー勤務実績状況の見える化や法改正への自動対応のほか、手当・賃金計算して給与ソフトに連携できるものもあります。
売上・コスト情報はすべて車番に紐づけ、車輌損益を管理
車輌台帳管理は、売上・コスト管理とあわせて仕組み化できると効率的になります。車検や整備などの記録は台帳管理しつつ、車番とコスト情報を一緒にシステム登録することで、すべてのコストを車番に紐づけ車輌原価を把握するのです。これに日報情報(売上や、有料道路・人件費などの運行コスト)を組み合わせれば、車輌別の損益管理が行えるようになります。求める原価管理精度(人件費などの妥当性、月次or日次管理)で運用難易度が異なるため、自社に合った方法を検討すると良いでしょう。
まとめ
運送業が課題解決を図ろうとするとき、「どの業務を効率化(改善)するか」を考えなければなりません。その切り口として、「ドライバー業務」「配車業務」「事務・管理者業務」の効率化ポイントを解説しました。
ドライバー業務では日報作成の自動化、配車業務では受注の電子化と配車業務のシステム化、事務・管理業務では業界特化側システムを利用することで請求や車輌損益管理、ドライバー労務管理が効率化されます。自社業務の改善ポイント探しと取り組みの優先順位ご検討に際し、ぜひ本コラムをお役立て頂ければと思います。