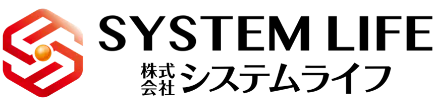こんにちは、システムライフ(SL)大学です。SL大学とは2022年に立ち上がった社内教育機関で、毎月勉強会を開催しています。その一部を学習ノートとして公開いたします。

食肉卸向けシステムで受注入力を実装するパターンが増えているので、傾向をまとめます。
どんなときに受注入力スタートが良いのか
納品業務は3つのフェーズに分けられる
まず、納品業務をザックリ分解すると、①受注→②出荷→③売上の3段階に分けられます。
①受注:得意先から電話やFAXなどで注文を受ける
②出荷:受注商品を在庫から出したり当日作ったりして荷揃えする
③売上:荷揃え結果(出荷重量)をもとに伝票発行して納品する
システム運用をどのフェーズからスタートさせるか
一般的な販売管理システムは、③のタイミングでシステム入力を開始します(売上入力&伝票発行)。システム運用のタイミングを繰り上げて①で受注入力を行うとしたら、システムで何ができるようになるのか考えてみましょう。
≪受注入力を行うことで効率化されることの例≫
・在庫の出荷予約(引当)ができるので、自由に売っていい在庫(有効在庫)を捉えられる
・受注加工を行う卸の場合、加工指示書をシステムから出力できる
・システムから出荷指示書(ピッキングリスト)を出力できる
・指示書にバーコードを印刷できるので、バーコード検品等が可能になる
受注入力からスタートしたほうが良いパターン
上記のことから、以下のような業務パターンや業務課題を抱えている業者は、受注入力からシステム運用をスタートさせると全体効率化に繋がる可能性が高いです。
・在庫引当てを行わないと当日欠品などの不都合が発生する(営業マンが多い業者など)
・受注内容をもとに加工指示書や商品ラベルを作成できる(受注加工がメインの業者)
・外部冷蔵庫への出庫依頼書を毎日大量に作っている(外冷利用メインの業者)
・受注とピッキング商品の照合チェックを機械化したほうが良い(誤出荷が多い業者)
・出荷前に計量ラベルを貼付し、受注ごとに重量を手書きメモして伝票発行する業者
最後の2つは、指示書にバーコードを印刷するからこそ改善可能になります。(受注と異なる商品やロットをピッキングしたら警告できる、商品バーコードの代わりに指示書のバーコードを使うことで受注に出荷重量を紐づけられる)
最大の壁、受注入力の手間を減らすには
受注入力スタートで後続業務を効率化させようとするとき、受注入力の手間はどうしてもネックになります(件数が多い、時間がないなど)。この問題を乗り越えるには、できるだけ入力を簡素化する(過去伝票の複写など)か、CSV取込で入力レスにする(Web受注、FAX-OCRやTEL音声の自動文字起こしソフト活用など)しかありません。
これらのどれを採用するかは、ヒアリングによって絞り込みます。受注手段(TEL、FAX等)の割合やFAX注文のフォーマット数で入力レスの選択肢があるかどうかを見極め、受注業務にかけられる人数や時間で受注入力スタートの可否を判断し、得意先業態(飲食店、小売り等)の割合や各社注文内容の固定化の程度で入力簡素化の実現性を確認していくイメージです。
≫関連コラム:食肉卸に必要な販売管理システムとは~ポイントと選び方
≫関連ノート: