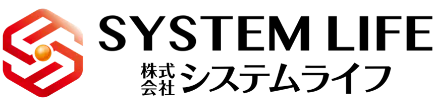こんにちは、システムライフ(SL)大学です。SL大学とは2022年に立ち上がった社内教育機関で、毎月勉強会を開催しています。その一部を学習ノートとして公開いたします。

不定貫対応WMSの、主な特徴的機能を纏めます。食肉などの不定貫生鮮品を取り扱う冷蔵冷凍営業倉庫向けです。
主な機能①入荷ロットNo管理
不定貫WMSでは入荷ロットNoを付番して荷主に実績報告し、両社同じロットNoで在庫管理する、というのがよくある流れです。なので荷主からの出庫指示は、品名に加えロットNoまで指定された形で受けます(※背景としては、同じ商品であっても賞味期限や産地などの違いを荷主側で管理&出し分けたいため)。一般的なWMSだと品名で出荷指示を受け、倉庫側が在庫を引当ててから出荷作業を行うため、そういった一般商品も取り扱う倉庫のWMSは、両方のやり方に対応しておかなけばなりません。
補足ですが、WMSでは在庫の引当て処理は自動引当てが多く(※先入れ先出しなどのルールを予め設定)、引当てボタン押下で処理完了となります。これを指示No単位で行うか、まとまった単位で行うかは要検討。
主な機能②出荷時の重量検品
不定貫商品の出荷では、荷主から「ロット●●を10ケース出荷して」という指示をFAXやEDIで受け取ります。これをWMSに入力したりデータ取込したりして出荷予定データを作り、指示書を発行する流れです。そしてここからが不定貫特有の業務ですが、10ケースを出庫したらケースラベルの重量バーコードをハンディ検品時にスキャンする等して重量を記録し、1ケースずつの重量明細を表示した伝票を作らなければなりません。伝票の呼び名は、量目表・出庫伝票・出庫明細書など様々で、作成した伝票は配送ドライバーに渡され、最後は納品先に渡ります。
尚、これらは大変手間のかかる作業なので、入出庫料とは別に「伝票作成料」などの費目で荷主に請求されることも多いです。当然、請求データ作成時にはこれらの実績も集計することになります。
主な機能③ロットの一部を名変する時の重量検品
まず一般的な名義変更の処理ですが、指定された在庫の寄託者コードやロットNoを変更するほか、場合によっては商品コードを振り替えたりもします(寄託者企業が使用する商品コードに合わせるため)。不定貫商品の名変ではさらに、「名変した重量が何kgだったのか」を荷主に報告しなければなりません。指定されたロット300ケースを丸ごと名変するのであれば入荷時の重量=名変重量としますが、例えばそのうち100ケースを名変する場合、出荷と同じようにハンディ検品などで重量の記録が必要です(※ハンディに専用メニューを設ける)。尚、丸ごと名変する場合は②のとおり出荷時に重量記録をとっていきます。
補足ですが、名変後の寄託者にとっては名変=入庫にあたるので、入出庫料は名変後の寄託者が負担するのが一般的(名変前の寄託者は入庫時にすでに入出庫料を払っている)。保管料については、名変事業者間でいつまでorいつから負担するかがその時々で取り決められます。結論、入出庫料・保管料ともに名変入力時に都度設定できる仕様が理想です。
主な機能④在庫数ゼロ時の重量精算
上述のとおり、出庫や名変のタイミングでケースラベルに表示された重量を記録し在庫重量から差し引いていくと、ケース数がゼロになったタイミングで在庫重量もゼロになるはずです。が、ケース数ゼロにも関わらず重量がグラム単位でデータ上残ってしまうことがあります(※詳細は別ノート参照)。このため不定貫WMSでは、出切って重量残りが発生した在庫データを照会したり、それを簡単にゼロ精算できるような機能が必要です。
補足ですが、出切れ時の重量残りは入庫時の登録重量が正しくないために発生します。その重量は荷主側から申告されたもので、荷主も正確な重量を知らないことがあるため、高単価商品などでは入庫時に重量検品まで依頼されることもあるようです(検品手数料が発生)。
主な機能⑤重量建ての料金設定
不定貫商品の場合、倉庫側は荷主に請求する入出庫料や保管料をkg単価(いわゆる「重量建て」)で取ることも多いかと思います。なので請求データを作成する際は、入出荷の重量実績を寄託者/締日単位で集計する処理を行います。自前の運送部門を持つ営業倉庫だと、運賃も重量建てで設定したりするので、WMSに販売管理機能まで設ける場合は、入出荷実績データと運賃マスタを掛け合わせて運送収支管理や運賃請求書を出力したりします。
補足ですが、売上/請求処理時の料金計算方法は重量建てのほかに、個建て(1箱いくら)、保管料の坪貸し(月極めの固定料金)、運賃の車建てなど色々あり、寄託者ごとにこれらを設定できるよう考慮が必要です。
≫関連ノート:
≫関連ノート: