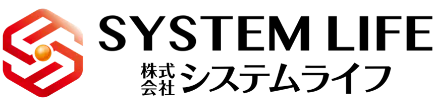こんにちは、システムライフ(SL)大学です。SL大学とは2022年に立ち上がった社内教育機関で、毎月勉強会を開催しています。その一部を学習ノートとして公開いたします。

RFIDタグの導入検討に必要な知識を纏めるシリーズ。ここではRFIDタグそのものの基礎知識を纏めます。
RFIDの構造と、バッテリー有無による電波強度の違い
RFIDの基本構造は、ICチップ+アンテナです。加えてバッテリーを有するものがあり、これを「アクティブ型タグ」と呼びます。バッテリーがないものは「パッシブ型」と呼ばれ、当社の開発事例で取り扱ったことがあるのはパッシブ型タグのみです。
ではパッシブ型タグが電波を出したり受け取ったりする際の動力源はどうしているかというと、リーダー端末から電波を照射し、その電波をタグ側のアンテナで吸収して発電する仕組みとなっています。したがって、パッシブ型タグが出す電波の強度はリーダー側の電波出力強度に依存します。タグ電波が弱い=長距離通信に向かないということなので、逆に近距離でしか通信しないのならパッシブ型で良し、ということです(交通系ICや某アパレルブランドの値札タグがその代表例)。
尚、アクティブ型タグはバッテリーを内臓しているぶん電波を長距離(数十メートル単位)で自力で飛ばすことができますが、バッテリー寿命がきたら当然ながらタグ交換が必要です。バッテリー寿命は、通信頻度によりますが年単位と言われています。
RFID電波を通す素材、通さない素材
Wi-Fiを思い浮かべてもらうと分かりやすいですが、電波というのは建材も通り抜けます。なのでRFID電波についても、段ボールなどの梱包材はもちろんのこと、木材や石膏ボードなどの壁は基本的に通り抜ける点をまず認識しておいた方が良いかと思います(これがデメリットとして働いた事例は別ノートを参照)。逆に、RFIDが電波通信しづらい環境は以下のとおり。
■ 鉄板の障害物がある
…鉄板は電波を反射する性質がある。逆に鉄板で囲われた場合は反射で電波が増幅し、その空間内の電波強度が増す。
■ RFIDタグが水や金属に触れている
…水や金属が電気を通す素材なので、タグが素材に触れた状態だと電気が素材に逃げてしまい電波を返せなくなる。湿気が多い環境も気を付けたほうが良い。
尚、RFIDタグはメーカー努力により「金属OK」「濡れても乾けばOK」などの商品が随時出てきているため、そうしたタグを採用することで乗り越えられる可能性はあります(ただし高コスト)。
ほかにもある、通信しづらい環境
上記の障害物由来以外にも運用上うまくスキャンできなかったケースがあったので、備忘録として残しておきます。↓
■ RFIDタグ同士が接触している場合
■ RFIDタグ(アンテナ)が折れ曲がっている場合(折った状態で保管などを行う布製品へのタグ貼付で起きがち)
RFID電波の周波数帯
上記でWi-Fiを引き合いに出しましたが、同じ電波通信でもWi-FiとRFIDでは使用する周波数帯が異なるのが一般的です。Wi-Fiが使用する帯域は2.4GHz/5GHz/6GHz、RFIDでよく採用されているのは、極超短波といわれる「UHF帯(860~920MHz)」になります。RFIDが使用する周波数帯は、ほかに「HF帯(13.56MHz)」や「マイクロ波帯(2.45GHz)」など。RFIDを使用する環境の周辺電波状況を鑑み、導入時にどの周波数帯のタグを採用するかを決めます(周辺電波との干渉がなるべく起こらないようにする)。
≫関連ノート:RFIDタグに持たせる情報と、書き込み方
≫関連ノート:RFID運用設計時の注意点まとめ
≫関連ノート:RFID活用の落とし穴と、回避方法
≫関連事例 :バーコードからRFIDに移行し、入出荷作業を大幅時短