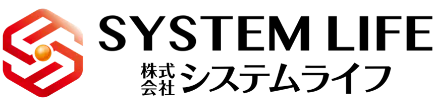こんにちは、システムライフ(SL)大学です。SL大学とは2022年に立ち上がった社内教育機関で、毎月勉強会を開催しています。その一部を学習ノートとして公開いたします。

基本に戻り、そもそも運送事業って何なのかを体系的にまとめます。
物流6大機能と、運送事業者が担うこと
物流6大機能は別ノートに纏めたとおりで、そのなかの「輸配送」というプロセスを運送事業者が担っています。とはいえ運送事業者の戦略は様々なので、保管機能(倉庫)を持つ事業者もあれば、さらに流通加工まで行う事業者も珍しくありません(当社のお客様の例で言えば、荷主から預かった部品同士を組み立てて出荷配送するなど)。
また「荷役」は物流倉庫や港湾事業者が担っているイメージが強いですが、トラックドライバーも荷役(=荷積み/荷卸し)を担う存在です。なのでデジタコには、荷役作業実績を記録する機能(荷役の開始/終了ボタン)が標準で備わっています。
運送事業の大分類:実運送か、利用運送か
日本の貨物運送事業は、主に「貨物自動車運送事業法」と「貨物利用運送事業法」という二つの法律に基づいて体系化されています。これらの事業は、実際に運送手段を持って運送を行う「実運送事業(貨物自動車運送事業)」と、運送手段を持たずに他の運送事業者を利用して運送を行う「利用運送事業」に大きく分けられます。(実運送は前者の、利用運送は後者の法律によって規制される)
貨物自動車運送事業(実運送)の3分類
①一般貨物自動車運送事業
不特定多数の荷主の貨物を、有償で自動車(軽自動車や二輪車を除く)を使用して運送する事業を指し、国交大臣or運輸局長の事業許可が必要です。この事業者の特徴(下記)を見ると、当社のお客様のほとんどが「一般貨物自動車運送事業者」なのが分かります。
■ 営業所ごとに5台以上の事業用自動車が必要
■ 営業所に併設または一定の距離内に全車両が収容できる車庫が必要
■ 運行管理者、整備管理者の配置が必要
≪補足1:宅配業者もこの事業の一形態≫
不特定多数の荷主の貨物を運賃を貰って運ぶという点では、日ごろ私たちが利用する宅配業者も同じです。宅配業者の特徴は、多数の小口貨物を都市間で効率よく輸送するために「積合せ」を行い、地域の営業所や物流センターで仕分けし、集荷配送を定期で行っていること。この業態は「特別積合せ貨物運送(特積み)」と呼ばれます。
≪補足2:車輌が足りないときは利用運送することもよくある≫
「一般貨物自動車運送事業」を行う当社のお客様は、空き車輌がなかったりすると傭車を使っているのは言うに及ばず。運送手段を持たずに他の運送事業者を利用して運送を行うということなので、傭車は利用運送にあたります。正確には「一般貨物~」のなかに「貨物自動車利用運送」という形態がある、という位置づけです。
②特定貨物自動車運送事業
単一特定(1社のみ)の荷主の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業を指し、①と同じく国交大臣or運輸局長の事業許可が必要です。荷主専属であることから、車輌のボデーに荷主企業の名前や製品広告をペイントしているものも多く見られます。当社の周辺でいえば、自動車メーカーが工場間で部品輸送する際や、食品メーカーの都市間輸送に使われる保冷車輌などが当てはまります。
③貨物軽自動車運送事業
他人の需要に応じ、有償で、軽自動車(三輪以上)または二輪の自動車を使用して貨物を運送する事業を指します。許可制である①②と異なり届出制(※届出先は運輸支局長)なので、事業開始の障壁が比較的低いと言えるでしょう。ECのラストワンマイル配送やフードデリバリーがイメージしやすく、小回りの利く地域密着型の配送業者として高いニーズがあります。
トラック配送の場合は軽トラックになるため、ナンバープレートは黒色(黒ナンバー)。ちなみに①②は営業車輌としてお馴染みの緑ナンバーですが、緑ナンバー・黒ナンバーの設定は、自家用車のナンバープレート色(普通車なら白背景+緑文字、軽なら黄背景+黒文字)をそれぞれ反転させたものです。
貨物利用運送事業の2分類
①第一種貨物利用運送事業【利用運送専業】
他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、第二種貨物利用運送事業以外を指します。車輌を持たないため事務所しか所有していません。事業許可制ではなく登録制で、荷主に対して運送責任を負わない業態=「運送取次業」とする場合は登録すら不要になりました。(運送取次業ではなく利用運送事業とする場合は、荷主に対して運送責任が生じる)
②第二種貨物利用運送事業【複合一貫輸送】
他人の需要に応じ、有償で、船舶運航事業者、航空運送事業者または鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し及び後続する当該利用運送に係る貨物の集配のためにする自動車による運送とを一貫して行う事業、を指します。端的に言えば「複合一貫輸送業者」のことです(複合一貫輸送については別ノート参照)。この業態は事業許可制で(第一種より厳格な審査が行われる)、下記の条件を満たす必要があります。
■ 幹線輸送に海運・航空・鉄道を利用すること
■ 集配輸送に貨物自動車運送事業者(緑ナンバー)を利用すること
■ 貨物軽自動車運送事業者(黒ナンバー)を利用する場合は第二種に該当しない
≫関連ノート:物流の役割をサプライチェーンから紐解く
≫関連ノート:ロジスティクスマネジメントと物流SIerの役割
≫関連ノート:複合一貫輸送の登場人物まとめ
≫関連ノート: