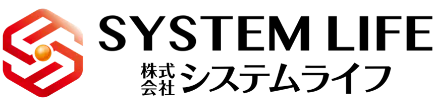こんにちは、システムライフ(SL)大学です。SL大学とは2022年に立ち上がった社内教育機関で、毎月勉強会を開催しています。その一部を学習ノートとして公開いたします。

ふだん当たり前のように開発している「量目表」とは何なのか、その役割をまとめます。
量目表の役割とは
量目表は「納品書に記載している取引重量の明細」というイメージが強いですが、smartBPCの考え方は「納品書=商流用の伝票、量目表=物流用の伝票」です。なのでsmartBPCは、売上管理メニューの中に「納品書発行」が、出荷管理メニューのなかに「量目表発行」がある作りになっています。
不定貫の倉庫業務では、出庫結果として量目表を作成する
納品書=商流伝票/量目表=物流伝票の役割については、モノを先に動かし伝票を後処理するシチュエーション、たとえば外冷から納品先に直送するケースを考えると理解しやすいです。
ある食肉卸が外冷に「商品Aを10c/s出庫して」と出庫指示すると、外冷は指示に従ってピッキングした商品Aの重量を10c/sぶん記録します。重量の記録は一般的にハンディを使うため、その重量データがWMSに取り込まれてWMSで量目表発行する流れです。(※倉庫によって量目表の呼称は異なる、詳細は別ノート参照)
納品書を作成するのは食肉卸
では外冷がそのまま一緒に納品書発行まで行うかというと、食肉卸の取引においては稀と言えます。外冷は在庫業務を委託されているだけであって、納品書発行に必要な情報=販売単価や売上計上日などは知りません。結果、外冷から出庫重量の報告を受けた食肉卸側が、自社システムで納品書を発行して郵送処理することになります。(量目表は外冷がモノと一緒に出荷)
納品先にモノが届いた時に納品書(納品先にとっての仕入伝票)はまだ届いてないわけですから、納品先側はいったん量目表をもとに荷受けし、後日仕入伝票が届いてから仕入計上を行います。まさに物流伝票と商流伝票で明確に役割分担されたパターンです。
自社からの出荷分は、納品書一体型とするケースも
上記は外冷からの出荷でモノと納品書が別々に動くシチュエーションでしたが、自社倉庫からの出荷でも、事務員配置の問題などで納品書を事後発行せざるを得ないケースもあります。(これに対応するため、smartBPCはハンディ出荷検品すればとりあえず量目表発行だけはできる仕様)
ただ話を聞く限り、自社倉庫からの出荷では100%モノと納品書が一緒に動く(納品書発行してからトラック出発する)パターンが多い印象です。納品書と量目表を同じタイミングで発行~納品先に渡すため、そうなると納品書/量目表が独立して存在する必要がなくなります。現に、量目表一体化型の納品書を使用する食肉卸も少なくありません(納品書の備考欄に表示することも)。
補足:納品先ではどのように入荷チェックするのか
上記のとおり、納品先側はモノと一緒に仕入伝票(量目表/納品書)を受け取ることになります。当然、伝票どおりに商品が届いたかの確認が行われますが、ここで量目まで照らし合わせる事業者はあまりいないようです。商品毎のc/s数だけ確認してOKな事業者もあれば、ハンディ入荷検品でラベル重量を取り、入荷予定データ(事前に入手した量目表/納品書情報をもとに予め作成)との総重量差異がないかを確認する事業者など、入荷チェックのやりかたは様々。
ちなみに商品毎のc/s数だけを確認して在庫受け入れとする場合、入荷重量は出荷元が申告した(量目表/納品書に記載された)重量を信用する、ということです。ハンディ入荷検品での重量スキャン運用を採用する場合は、自社の検品実績を入荷重量として取り扱うのと同時に、検品実績をそのまま在庫データとして使用できるメリットがあります。このあたりは、事業者がどのような在庫管理の在り方を目指すかで入荷検品方法が変わってきます(→別ノート参照)。
≫関連ノート:不定貫を取り扱う倉庫のWMS
≫関連ノート:食肉卸がロット管理・単品管理を導入する目的
≫関連ノート: