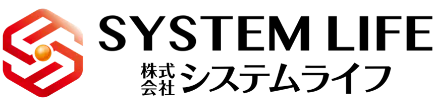こんにちは、システムライフ(SL)大学です。SL大学とは2022年に立ち上がった社内教育機関で、毎月勉強会を開催しています。その一部を学習ノートとして公開いたします。

ハンディ検品実装案件で取り扱うことの多い食肉標準バーコードについて、少し掘り下げて学びます。
食肉標準バーコードの基礎知識
AI識別子が付いた「GS1-128」が採用されている
国産ラベルで使われる標準バーコードは、正式には「食肉標準物流バーコード」と言います。GS1-128という種類のバーコードが使われており(このあたりの話は別ノート参照)、AIとして「重量」「製造年月日」「個体識別番号」といった食肉の物流業務に欠かせないデータ項目が定義されています。主なAI項目は以下の通り。
●01:商品コード(14桁固定)
●3102:重量(6桁固定)
●11:製造年月日(6桁固定)
●21:カートンID(可変長)
▲10:ロット番号(可変長)
▲7002:枝肉番号(可変長)
▲251:個体識別番号(可変長)
▲240:カット規格(可変長)
基本バーコード・補助バーコードの運用の実態
このように食肉業界はバーコード化したい項目が多いことから、バーコードは二段構成(基本バーコード+補助バーコード)を標準としています。上記●印が基本バーコード、▲印が補助バーコードに埋め込む項目です。
ただこの話はあくまで “標準” の位置づけで、基本バー/補助バーは現場ではかなり柔軟に運用されています。たとえば重量だけ、個体識別番号だけ、でバーコード化するパターンもあれば、基本バーに個体識別番号を埋め込んで補助バーなしとするパターンなど(下記のサンプル画像参照)。事業者の管理基準や使用するラベルサイズにあわせる形で、バーコードを2本表示とするか1本表示とするか、どのデータ項目を格納するか、を決めていくイメージです。※計量器側の設定で様々な項目組み合わせパターンを持っている模様

AI項目別の特記事項
商品コード(AI:01)
商品コードを埋め込む際は、9+JANメーカーコード7桁+標準品名コード5桁+チェックディジット1桁 の14桁構成と決まっています。「標準品名コード」というのがいわゆる部位を表し、5桁のうち1桁目は畜種(和牛/国産牛…)、次の3桁が部位コード、末尾1桁は自由、といった詳細なガイドラインが存在します。さらに、畜種なら1:和牛/2:国産牛…、部位コードなら420:うちばら/430:そとばら…と、コード体系まで標準化されています。
が、全国の食肉卸業者が自社のシステムでこの通りに部位コード(商品コード)を振っているかというと、そうでないことのほうが多いです。上述したコード体系は、日本食肉流通センターが定めた「コマーシャル規格」という部位の分割パターンに基づいて制定されていますが、コマーシャル規格どおりにカットすることもあれば、納品先からのリクエストに合わせて部位を切り出すことも実態として多いからです。(あと、自分たちが好きなように部位コードを振るため)
このような背景から、入出荷検品の要件として他社ラベルの部位情報を読み取る必要がある場合は、入荷元(メーカー/工場)別の部位コード変換マスタが必要になります。(入荷元の判別にはJANメーカーコードを使ったりもする)
カートンID(AI:21)
業者によっては、そもそも基本バーコードに埋め込んでいなかったり、ゼロ埋め(実質未使用)状態だったりします。埋め込む場合は概ね8~10桁程度で、「産地番号3桁+機械番号1桁+連番4桁」といった複数の要素で構成されます。在庫管理を行うにあたり、カートンIDをユニークNoになるよう構成して在庫No(在庫管理ラベル)代わりに活用することも多いです。
枝肉カットを外部委託している場合は、カット業者に「カートンIDにこのような項目を埋め込んでください(自社システムの在庫Noと被らないような項目構成を指定)」とお願いすることで、自社製造品と同じように入荷ラベル貼付が省略できる可能性があります。※カット業者側で計量器システム改修が必要になることもあるため、応じてくれるかどうかはケースバイケース。
枝肉番号(AI:7002)
枝番というと4桁ですが、【7002】として埋め込まれるデータは7~14桁と様々です。これも「工場番号2桁+枝番4桁+枝左右1桁」などのように複数の要素で構成されており、他社ラベルで枝番をバーコード取得する場合は「7002項目の何桁目からが枝番なのか」を入荷元(メーカー/工場)別にマスタ管理しておく必要があります。
個体識別番号(AI:251)
個体識別番号というと10桁ですが、【251】として埋め込まれるデータは10桁とは限りません(計量器側で可変長扱いとなっている)。他社ラベルで個体識別番号をバーコード取得する場合、「251項目の何桁目からが個体識別番号なのか」を入荷元(メーカー/工場)別にマスタ管理しておく必要があるのは枝肉番号と同じですが、個体識別番号のバーコード取得は実装需要が高いために、より注意しておく必要があります。
≫関連ノート:GS1-128バーコードを理解するための話。
≫関連ノート: