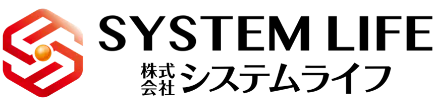こんにちは、システムライフ(SL)大学です。SL大学とは2022年に立ち上がった社内教育機関で、毎月勉強会を開催しています。その一部を学習ノートとして公開いたします。

当社システムで取り扱うことも多いGS1-128バーコードを理解するため、バーコードの成り立ちから整理していきます。
小学生でもわかるバーコードの仕組み
もともとバーコードの縦じま模様というのは、たとえば「1」という情報をある形(符号)で表現しようとして、「この白黒バーの並びと幅で“1”を表す」という考え方で出来ています。同じように2の場合、3の場合…とルールを作っていき、「12345」という情報を符号化(エンコード)した結果が、あのバーコードシンボルです。このような仕組みなので、情報量を増やそうとすると、バーコードは横に長くなっていきます。
ほかに同じような情報符号化の仕組みとして、モールス信号があります。(短点3回→長点3回→短点3回でSOSを表すなど)
主なバーコードの種類
バーコードが誕生してからというもの、エンコード方法の進化やルール整備が進み、現在では様々な種類のバーコードが存在します。当社案件で取り扱うことの多いバーコードを簡単に纏めておきましょう。
JANバーコード
最も聞きなじみがあり、POSレジや小売り商品の検品で取り扱うバーコードです。「数字のみ」「1つのバーコードは13桁 or 8桁」「2本のバー(黒)+2本のスペース(白)で1文字を表す」などの国際ルールに基づいて生成され、運用されています。尚、このバーコード規格は、国際的には「EAN」と呼ばれています。(JANは日本独自の呼称)
コード39、コード128
当社システムで在庫ラベルなどを生成する際は、「コード39」や「コード128」を使うことが多いかと思います。数字に加えてアルファベットなども扱えるのが、JANとの大きな違いです。特にコード128はエンコード効率が良い(情報圧縮してエンコードするので1桁を表すために必要な幅が少なくて済む)ので、ロットNoや日付などできるだけ多くの情報を格納するのに使いやすいバーコードとなります。
コード128の進化版、GS1-128
GS1-128バーコードの登場
上述した理由から、コード128は特に物流用途のバーコードとして広く使われるようになりました。そのなかで「製造日はYYMMDDの6桁で表現しよう」「製造日の情報にはこのマークをつけよう」といったバーコードルールを定め、業者間の垣根を越えて物流プロセスを円滑にしようとする動きが生まれました。そこでコード128をベースに再定義されたのが、「GS1-128」というバーコードです。
GS1-128の特徴:アプリケーション識別子(AI)
GS1-128はコード128の派生型なので基本的なエンコードルールは同じですが、上述した「製造日の情報にはこのマークをつけよう」を実現するために、“このマーク”にあたる「アプリケーション識別子(AI)」がバーコードに組み込まれます。AIは数字で表現され、バーコードシンボル下に値を表示する際は、(11)251031 のように括弧で囲うルールとなっています。この例では、「11」が製造日のAIで、「251031」が読み取るべき日付情報です。
参考:AI一覧表(流通システム開発センターのサイトに飛びます)
GS1-128が活用されている場面とは
このようにAIを定義し、各社がそれに則ってバーコードプリントすることで、その商品のバーコード運用が業界標準化されます。この仕組みを取り入れている業界として有名なところでは、食肉業界(食肉物流標準バーコード)や、コンビニなどでの公共料金の代理収納(払込伝票バーコード)などがあります。
参考:国内のGS1-128シンボル利用動向(流通システム開発センターのサイトに飛びます)
≫関連ノート:食肉標準バーコードまとめ
≫関連ノート: