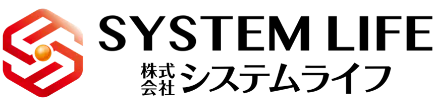こんにちは、システムライフ(SL)大学です。SL大学とは2022年に立ち上がった社内教育機関で、毎月勉強会を開催しています。その一部を学習ノートとして公開いたします。

海外から輸入した貨物が検疫される(通関の手前)までの大まかなプロセスをまとめます。
①入船してコンテナが降ろされる
輸入商品を積んだ船が港に入船すると、海上コンテナはガントリークレーンなどを使ってすべて降ろされ、船は別のコンテナを積んで出発します。船から機械を使ってコンテナを降ろしたりコンテナヤード(CY)で一時保管する事業者は「港湾運送事業者」と呼ばれ、免許制です(このへんの話は別ノート参照)。ここで荷役料や保管料が発生しますが、このあたりは着荷主(輸入事業者)に直接請求されるというよりは、通関業務を行う乙仲業者がまとめて輸入事業者に請求するパターンが多いようです。ただ、通関業務については港湾運送事業者が事業として行っているケースもあり、そのあたりは様々。
補足:ターミナルハンドリングチャージとは
船からコンテナが降ろされると、乙仲業者は船会社に対して「ターミナルハンドリングチャージ(THC、運賃とは別に徴収される追加料金)」を支払う必要があります。本来は荷主が支払うべき費用ですが、THCを払わないとCYからコンテナを引き取れない仕組みなので、便宜上、乙仲業者が立て替えている形です。(乙仲業者→荷主への請求明細に「立替金」という費目で載っていたりする)
②CY→保税倉庫に輸送する
CYにもキャパシティがあるため、未通関だからと言ってコンテナをずっと置いておくわけにはいきません。一般的には港に到着後数日以内に、トレーラー車を持つ運送会社が海上コンテナごと引き取りにきます。このコンテナ輸送では、輸送日や荷卸し先倉庫のほか、引き取るコンテナ番号もドライバーに通知されています(※ちなみにCY側も誰にどのコンテナを渡すかを把握している)。
この運送会社への指示を誰が行うかについては、荷主であることもあれば、荷主に依頼された乙仲業者であったり港湾運送事業者であったりもします(それによって荷主がどこからコンテナ陸送料を請求されるかも様々)。
補足:倉庫業者に入庫依頼をかけるのは荷主
荷主は入船予定日の連絡を受けると、倉庫業者に対し「●月●日にこういう商品が入りますよ」という事前通知(入庫依頼)をかけることになります。荷主がCY→倉庫への輸送便を手配する場合も、概ね同じタイミングです。
ちなみに着荷主は「船がどの港に着くか」を把握しており、基本的には船会社ごとに使用する港が決まっています。船便を誰が手配するかは輸入事業者が輸出元とどのような貿易取引条件を結ぶかにより、たとえば輸出元が船便を手配して取引相手(輸入事業者)に商品代金と一緒に海上運賃を請求する取引形態は「コストアンドフレート(CFR、日本語訳は運賃込み条件)」と呼ばれます。
③デバンニングして入庫後、検疫
コンテナが倉庫に到着すると、コンテナから荷物を降ろす作業=デバンニングが行われます。デバンニング作業も荷役料の一つとして荷主に請求されます(ここも倉庫が請求したり、乙仲業者が請求したりと様々)。
検疫は、このタイミング(保税倉庫に入庫後)に行われるケースが多いようです。食肉製品は必ず動物検疫を通さなければならず、動物検疫所による書類チェック+場合によっては現物確認(モノやシール表記が書類どおりかなど)が行われます。さらに食品は必ず食品検疫所による検疫(大腸菌チェックなど、動物検疫と同じく書類チェック+場合によっては現物確認)にかけられ、検疫合格後は「試験成績証明書」が発行されます。
ちなみに食品衛生法で食品別に「規格基準」が定められており、該当する食品は入庫品の一部を抜き取って菌数や添加物などを“自主検査”の名目で検査し、基準どおりである旨の証明書を発行します。有効期限が1年あるためサンプル抜き取りは基本的に年1回で良いとされていますが、生食用などは毎回(輸入ごとに)自主検査を求められるようです。
検疫合格した商品のみ、通関手続きに入ります。
補足:検疫にひっかかった輸入品のゆくえ
検疫で引っかかった商品は、国内に入れることができません。なので輸入元への送り返し(通称:積み戻し)や焼却処分(通称:滅却)になるのですが、輸入元は送り返しても受け取らないことが多く、専門業者が引き取って滅却することが多いようです。
こうなると荷主が損を被ることになりますが、荷主が貿易保険に入っている場合、滅却後に発行される廃棄証明書を保険会社に提出すると、輸入元に支払った商品代金が保証されたりします。実態としては、あまりに保険申請をしすぎると保険料が上がってしまうため、滅却時に保険適用するかは都度判断しているようです(輸入元に検疫NGの事実を伝え、返金や次回値引などの交渉を行うことも)。
≫関連ノート:海陸複合輸送の登場人物と全体の流れ
≫関連ノート: