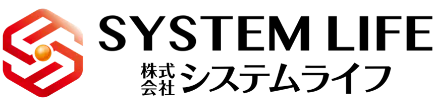こんにちは、システムライフ(SL)大学です。SL大学とは2022年に立ち上がった社内教育機関で、毎月勉強会を開催しています。その一部を学習ノートとして公開いたします。

RFIDタグの導入検討に必要な知識を纏めるシリーズ。ここではRFIDシステム開発のポイントを纏めます。
関係のないタグを読まない工夫
別ノートで説明したとおり、電波は一般的な建材は通り抜けます。壁の向こうに保管している商品のRFIDタグも、場合によっては読み取れるということです。これが吉となる運用もありますが(棚卸など)、たとえば入出荷検品では特定の商品に対して処理を行いたいため、この電波の特性がデメリットに転じます。この問題を乗り越えるにはいくつか方法があります。
電波を遮断する障害物を設ける
まず、「RFIDをオープンスペース環境で取り入れるのは一筋縄ではいかない」と考えたほうが良いです。物流現場で検討されがちな入出荷検品では、処理対象とする商品/しない商品の切り分けが必要になります。その切り分けを物理的に行う方法として、当社事例でも使用実績があるのが専用パーテーションの設置です。電波を吸収する素材で出来ており、パーテーションで検品エリアを囲い込むことで「この範囲のタグしか読まない」という状況を作ります(ちなみにパーテーションは1枚あたり数十万円)。某アパレルブランドのRFIDレジも、同じように隣レジの商品タグを読み取らないよう専用素材で囲われたつくりをしています。
RFIDタグの読み取り環境を精査する際は、「リーダー端末から半径●mの範囲にあるタグに働きかける」イメージを持って検討し、適した環境づくりまでセットで行う必要があります。
処理対象としないタグは読み捨てる
システム側での処理になりますが、「読み取ったデータのうちある条件に該当するデータだけを処理して、ほかは読み捨てる」というような手法もよく取られます。たとえば出荷検品であれば、出荷可能な商品の対象シリアルNoをシステム側で把握しておき、スキャン時にそのシリアルNo以外のタグデータは無視するような処理です。当然ながら重複(いちど読み取った)データの排除処理なども必要になるので、RFID検品ではプログラム制御を細かく入れる場面が増えます。
リーダー端末の出力強度を調整する
別ノートで説明したとおり、パッシブ型タグが出す電波の強度は、リーダー側の電波出力強度に依存します。タグ電波が弱い=近くのタグしか読み取れない、ということなので、読み取るタグを特定する目的であえてリーダー端末の電波強度を弱く設定するのも有効です。電波強度は入力画面ごとに制御可能で、当社の開発事例でも機能ごとに強度を使い分けています。
基本的にリーダー端末は大きく「高出力タイプ」と「中出力タイプ」に分けられ、中出力タイプは特定のタグを読み書きしたいときに採用します。高出力タイプだと半径5~6m内にあるタグは割と余裕で読めますが、電波強度があるぶん壁の向こうにあるタグも読んでしまうので上述の対策を取ります。あと、高出力タイプ(電波出力1W以下で高出力に分類されるリーダー)を利用する場合、総務省への電波利用申請が必要な点にも注意。(近くに医療機関などがあったりすると利用許可が下りない可能性も)
その他の注意点
ほかにも注意点があるので、備忘録として残しておきます。
■読み取り速度について
…処理内容にもよるが、1件ずつDB処理が入るとスキャン処理自体に時間がかかる恐れがある。特にリーダー端末がハンディターミナルタイプ(処理PC+入出力装置が一体型)の場合、処理性能が非力になりがちなので注意が必要。処理PCにタブレット端末、入出力装置にリーダー端末を使いBluetooth通信などで構築すると、処理性能がPCスペックになるので問題は起こりづらいかも。
■リーダー端末について
…高出力タイプを利用する場合、電池の消耗が異常に早くなり1つの電池パックで半日持たなかったりする。電池パックのみ追加購入できればいいが、電池パックだけの充電器が販売されていないと本体ごと購入するなど追加費用がかさむ恐れがある。1日利用してどれくらい電池が持つかの事前チェックは必要。ちなみに高出力タイプのリーダーは、長時間持っていると地味にしんどくなる重さ。
≫関連ノート:RFIDタグの基本的な技術知識まとめ
≫関連ノート:RFIDタグに持たせる情報と、書き込み方
≫関連ノート:RFID活用の落とし穴と、回避方法
≫関連事例 :バーコードからRFIDに移行し、入出荷作業を大幅時短