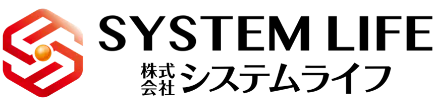こんにちは、システムライフ(SL)大学です。SL大学とは2022年に立ち上がった社内教育機関で、毎月勉強会を開催しています。その一部を学習ノートとして公開いたします。

配送業務のシステム化に不可欠となる「受注入力」について、正しく設計するために業務イメージの解像度を上げます。
そもそも運送業界における受注とは
運送会社にとって注文とは、「●月●日に、この荷物を、●●から●●に、●●円で運んで」という配送依頼のことです。配送金額は一般的に距離(発着地)や配送する荷物の内容・量などによって決まるため、配送依頼がきたら車輌の空き状況を確認(配車計画)しつつ見積を出し、合意してはじめて「受注」となります。
とはいえ輸配送ビジネスの仕方は事業者によって異なり、決まったダイヤ(配車計画)を前提に受注を取ったり、予め荷主と運賃表(タリフ)を取り決めたうえで日々の配送依頼に対応したりと、ビジネス形態によって受注の在り方もアレンジされていきます。
ビジネス形態ごとの受注のイメージ
例1)建築現場への輸配送を行う事業者の場合
たとえば建築現場への荷物輸送の場合、木材などの建築部材を集荷先A→工事現場に運ぶイメージです。現場は工事が終わるごとに変わっていくので、発着地がどこかは都度確認が必要になります。また同じ現場への配送でも、日によって運ぶモノが柱などの大きな木材だったり、窓ガラスなどの上積みできない荷物だったりするので、それらの内容によって準備する車輌のサイズや運賃が決まります。
例2)車輌輸送を行う事業者の場合
車輌輸送の場合、運ぶ荷物=車です。荷主から配送依頼を受ける際は、運ぶ車を間違えないよう、ナンバープレート番号のほかメーカー/車種/色なども指示されます。尚、自動車工場などから出荷された新車を輸送する場合、ナンバープレートがありません。オークション会場間を中古車輸送する場合は、その日の落札結果に応じて輸送する車種や台数が変わります(落札が多ければ輸送台数が減る)。どのような車輌輸送を行っているかで、受注情報が変化することも覚えておきましょう。
発着地については、自動車メーカーと事前に配送契約を結んだうえで、自動車工場~港、PDIセンター~ディーラー店舗などある程度パターン化されていることが多いです。これらの内容によって準備する車輌(キャリアカーの種類)や運賃が決まります。
例3)荷主店舗への定期配送を行う事業者の場合
スーパーやコンビニ配送を想像した場合、小売業者側の商品補充に合わせて配送トラックを毎日、定期(朝便/昼便など)で走らせるイメージになります。予め配送コースを設定して各店舗を回るルーチンなので、「●月●日に、この荷物を、●●から●●に、●●円で運んで」というデイリーの配送依頼がほぼ発生しません。代わりに、月次や契約(料金)改定などのタイミングで、「来月はこのコースで●●円で運んで(運びましょう)」と取り決めます。この時点で受注完了しているイメージです。
受注の在り方に応じて、受注機能の作りも変化
受注業務をシステム化するとき、受注の在り方によってどのように機能要件が変わってくるのかを、上記を例に考えてみます。
【例1】建築現場への輸配送
■建築現場は変動、住所情報のみの可能性もある ≫発着地はフリー入力可とする
■工事期間は何度も配送が発生する ≫発着地は履歴管理が必須
【例2】車輌輸送
■輸送品目が車である ≫メーカー・車種・色などを登録可とする
■発着地はメーカーとの契約に応じてパターン化 ≫パターン設定で入力省略
【例3】店舗への定期配送
■一定期間分のコース配送依頼を受ける ≫日次登録ではなくマスタ化
■物量増の場合、契約トラックに乗りきらない可能性がある ≫スポット配送対応を可能としておく
≫関連ノート:運送会社の料金計算
≫関連ノート: