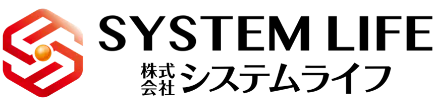こんにちは、システムライフ(SL)大学です。SL大学とは2022年に立ち上がった社内教育機関で、毎月勉強会を開催しています。その一部を学習ノートとして公開いたします。

受注入力や売上入力をシステム設計する際に必要となる、料金計算の基礎知識をまとめます。
料金計算の基礎知識
料金計算の公式
まず大原則として、あらゆる業界において料金計算の公式は「数量×単価=金額」です。そして、算出した金額に対して消費税を計算していきます。(※単価に消費税を含める=内税のケースもあります)
システム開発では受注入力や売上入力でこのような入力が発生しますが、ここで職種や企業ごとに特徴が出やすいのが「単価」です。同じ商品でも得意先ごとに販売単価を変えたり、商品ごとに「一律●●円」と決めて定期的に単価改定を行ったり、同じ得意先・同じ商品であっても取引ごとに販売単価を変えたり、といった感じ。その企業の単価の決め方に合わせて、料金入力の仕様を決めていきます。
運送会社の単価の決め方
モノ売りではない運送会社であっても、「数量×単価=金額」というロジックは変わりません。ただ運送業界の単価の決め方は特徴的なので、イメージしやすいように身近な例をあげてみます。
■宅急便の場合:「箱が80サイズで、関東→北海道までの配送なら、●●円」
■引っ越しの場合:「量が2家族分(=2tトラック手配)で、配送距離50kmなら、●●円」
■トラック貸出の場合:「軽トラックで、12時間パックなら、●●円」
上記のように、運送業界の単価設定は要素と要素の掛け合わせで決まり、それに数量(何箱/何台)を掛けて料金を計算します。
運送会社の料金計算の仕方
車建ての料金計算
上述した例、「引っ越しの場合」「トラック貸出の場合」というのは、いわゆる車建てビジネスです。荷物の個数ではなく、輸送に使用する車輌1台あたりの料金を設定する方式を指します。例にあげた単価決めの構造を読み解くと、こうなります。
単価 = 車種(2t車/4t車/トレーラー車など)× 距離 or 時間
なお「引っ越しの場合」については、配送注文時に量をヒアリングし、運送会社側が車種を決めるプロセスが発生しています。これはBtoC配送に関わらず、BtoB配送でも同様のことが発生します。補足として、BtoB配送(特に物流業者間)における量の伝達は、箱数のほか才数で行われることがあります。※才数については別ノート参照
個建ての料金計算
上述した例、「宅急便の場合」というのは、いわゆる個建てビジネスです。貨物1個/1箱あたりの設定料金を基準に料金を算出する方式を指します(荷物の量が都度変動するケースで採用されることが多い)。単価決めの構造は、宅急便をイメージするとこうです。
単価 = 1個/1箱あたりのサイズ種別 × 距離(関東の料金表なら、北海道/東北などの配送先エリア)
なお宅急便以外でも個建てビジネスはあり、単純に個口当りで設定したり、重量や容積等の量にたいして単価設定したりします。たとえば物流倉庫Aから配送センターBへ荷物を運ぶ定期仕事を請け負った際に、1箱または1kgあたり●円、と料金設定することがあります。この単価決めの構造は、
単価 = 1箱/1kgあたり●円
と単一要素で成り立ちます。(あとは公式通り「数量(何箱/何㎏あるか)」を掛けて料金計算するだけ。補足として、「何kgあるか」については容積換算重量を用いる場合あり≫詳細は別ノート参照)
基本料金(運賃)以外の請求費目
上記で算出した配送料金以外にも、配送で発生する様々な付帯費用を荷主に請求することがあります。たとえば以下の通り。
・利用運送手数料
・待機時間料
・積込/取卸料
・附帯作業(組み立て設置、手作業)
・実費(燃料サーチャージ、有料道路利用料など)
これらについても、受注入力や売上入力で「単価(予め作業単価を設定)×数量(一式など)」のような形でシステム入力を行い、請求書に記載する流れです。
≫関連ノート:運送会社の受注業務とは
≫関連ノート:容積換算重量の基礎知識
≫関連ノート: