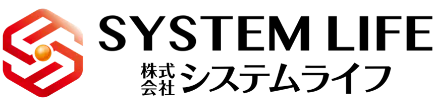こんにちは、システムライフ(SL)大学です。SL大学とは2022年に立ち上がった社内教育機関で、毎月勉強会を開催しています。その一部を学習ノートとして公開いたします。

自社倉庫で輸入肉を取り扱う食肉卸業者にパッケージ導入する際の注意点です。輸入肉を名変購入して外冷で保管する場合については別ノート参照。
輸入肉の商品ラベルと重量表示
輸入肉の重量は、ポンド表記が多い
輸入肉の箱にも、国内品と同じように内容重量が表示されたラベルが貼付されています。概ねバーコード付きで、重量データが格納されている確率も比較的高いようです。(それでも国内品と同じく100%ではない)
重量データというと「●kg」ですが、ヤードポンド法を採用しているアメリカだと重量は「●lb(ポンド)」で取り扱うため、商品ラベルの重量表記やバーコードの重量データはポンド値となります。輸出商品については便宜的にキロ値も(小さく)表示されてありますが、それでもバーコードに格納されているのはポンド値であることが多い印象です。
日本と同じメートル法を採用する他国の輸入肉ラベルについても、重量はキロ・ポンドの両方を表示していることが多く、バーコード格納重量はキロ値が基本ですが、アメリカ向け商品だとポンド値の可能性もあります。
ポンド⇔キロの換算処理
ポンド→キロ/キロ→ポンドの換算を行う際は、国際的に「1kg = 0.45359237lb」の係数を使って算出すると決まっています。ただ、決まっていると言いつつも小数桁数が多いため、小数第4位を切り上げて「1kg = 0.454lb」としたり、小数第5位を切り上げて「1kg = 0.4536lb」としたりと、取引者間でかなり柔軟に設定できる模様。
余談ですが「1kg = 0.45359237lb」という係数も、ひと昔前は「1kg = 0.45359243lb」と若干異なっていたようで、数学的見地からミクロレベルで見直されることもあるようです。(実務上は少数の途中で切り上げした値を使うため影響なし)
smartBPC運用への影響
輸入肉バーコードを使って重量検品する場合に、考慮が必要
入出荷時にラベル重量を目で見てメモするアナログ運用の場合は、ラベルに表示されているキロ重量を拾ってそれをシステム登録するだけなので機能考慮は不要ですが、バーコードマスタを使って重量をバーコード入力する場合は考慮が必要です。この運用をするために必要なシステム設定は以下のとおり。
①その商品のバーコードに格納されている重量は、キロ値かポンド値か
②ポンド値の場合、バーコード取得するポンドの有効桁数(99.99 なのか、99.9 なのか)
③取得したポンド値をキロ値にする際の換算係数(少数第何位で切り上げた/切り捨てた値を使うのか)
④キロ値に換算したあとの端数処理
一般的に、①は商品マスタに設定し、②はバーコードマスタに設定します。③④については得意先から換算係数を指定されるケースもあるようで、その場合③④は得意先マスタに設定することになります。得意先から特に換算係数の指定がなければ「一律で0.454!」などと会社マスタに設定すれば良さそうですが、実際のところ、その商品の仕入元が使った換算係数を使わないと仕入伝票重量との誤差が生じたりするため、商品マスタに設定するパターンもあります。
バーコードマスタの注意点と、OCRの活用
上述のとおり、輸入肉ラベルバーコードを使って重量スキャンするには、バーコードマスタが必要です。バーコードマスタは一般的に商品コードごとに登録します。このため、商品コードとバーコード仕様は常に1対1でないと成り立ちません。例えばショートプレートでもUS産、カナダ産などで取り扱いがあれば、商品コードそのものを分けておく必要がある、ということです(※同じ原産国でもブランド/メーカー違いの取り扱いがあれば、それも同様)。
ちなみに、同じ商品(原産国もブランド/メーカーも同じ)であっても製造工場によってバーコード規格が微妙に異なる、というのも実態として発生しており、どちらで来るかが分からないため結局バーコードマスタが使えなかったという事例もあります。
尚、重量のみの取得ならOCRでも問題なく運用できるのは、当社の導入事例で確認済みです。そもそもバーコードを使わないやり方であれば、「同じ商品にも関わらずバーコード規格が変わる」「バーコードにそもそも重量データが格納されていない」などの問題を乗り越えることができます。
輸入肉でも日本式ラベルが貼付されるパターン
グローバル経営を行う大手食肉卸では、海外の食肉加工業者と提携したり現地法人や出張所を置いたりして、自社の海外工場のような位置づけで直接運営を行ったりしています。そうすると工場の生産ライン(加工方法、使う機械、品質管理など)は日本企業側がコントロールすることになり、どのようなラベルを出すかも決めることができます。
このような背景から、大手食肉卸が直接海外から仕入れる輸入肉には、食肉標準ラベル(AI識別子が付いたGS1-128バーコード)が貼付されていることも少なくありません。その場合、輸入肉であっても国内品と同じシステム仕様で物流業務を行うことができます。
≫関連ノート:出切精算が発生する背景と、システム処理
≫関連ノート: